2022年10月25日
今回の対談相手である永井紗耶子さんは、2010年にデビューし、2020年に第10回本屋が選ぶ時代小説大賞などを受賞した小説家。よっぴーとは大学時代からゼミが同じで顔なじみであったという仲だ。日本の歴史について造詣の深い永井さんから語られる「明治期になり、失われたもの」とは?そして、歴史を読み解く上で、よっぴーと石川善樹さんの著書『むかしむかしあるところにウェルビーイングがありました』に共通するものとは?
 吉田尚記
吉田尚記
吉田 大学時代に同じゼミの先輩・後輩なんですよね。
 永井紗耶子
永井紗耶子
永井 私と吉田さんがめちゃくちゃ喋るので、先生に「吉田と永井以外の人で意見のある人?」と言われていましたね。当時、吉田さんが「デジタル多チャンネル時代が一億総多チャンネルになり、今後は全員オタクになっていく。だから、マスに訴えるのは意味がない」と話していた。「パッケージ化された人生は崩れていく」とも。20年以上を経て、まさにその通りになっていますよね。
吉田 僕の中では少しずつ精度を上げながらずっと同じこと考えている気がする。永井さんは、いつから歴史小説を書いていたんだろう。
永井 実は中学時代から書いているんですよ。でも小説書いていることは誰にも言わなかった。大学出て産経新聞の記者になったのも、司馬遼太郎さんが産経新聞出身だから(笑)。歴史小説を書くのに、決定的に足りなかったのが仏教の知識で。古典の文献を読んでいると、仏教の知識が必要なのだけど、歴史学の中で仏教を学んでも全くわからない。本格的に小説家になろうと、フリーライターをしながら佛教大学の大学院で日本霊異記という説話集の研究で修士号を取りました。そこからもう一回、古典を読み解いてみると、落語も能もそれこそ昔話も、ことごとく仏教的世界観が流れていて。その知識があると、資料の理解度の速さが違うんですよね。私はずっとミッションスクールで学んできたので、キリスト教的な価値観は入っていた。そうするとそれぞれの違いがハッキリしてきたんです。
最近、面白いなと思うのが、同世代の歴史小説家が負けた側の物語を書くことが多くなっていること。勝ち進むことの正義感みたいなものが、バブル期に最盛を迎えて、そういうストーリーに一度酔って、今はそれが戻りつつある形なのかなぁと。
吉田 2020年の大河ドラマも明智光秀の『麒麟がくる』だったし。
永井 判官びいきというけど、もともと日本にはそういう文化があるんだと思う。源頼朝に討たれた義経が主人公になる歌舞伎も然り。能だって幽霊か鬼が主人公なので、だいたい死んでいるか負けている人。そう考えると鎮魂歌が圧倒的で、ヒーロー万歳という話の方が少ない。
吉田 確かにそういうものは講談ぐらいにしかないよね。
永井 江戸のカルチャーはゆるゆるなんだけど、そのわりに落語然り、ジャーナリスティックでもあるなと思っていて。忠臣蔵がまさにそう。言いたいことを歌舞伎や落語にのせて、庶民にわかるようにコミカルにできる。そんな隠れインテリな人が一定層いたんだろうなと思えて。それに、江戸のカルチャーはある意味、多様性も感じます。女性の権利も、明治に入って急に圧倒的に縮小される。だから江戸時代の女性はイキイキと書けるんだけど、明治期だと女性を登場させてもすごく書きづらくなるんですよね。
吉田 明治になると、軍隊を作るために失われるものも多かったんだろうね。
永井 明治の段階で捨てたものは、つまりは「多様性」だったのかなと。あとは、廃仏毀釈で、旧来の宗教観を壊したことも大きい。つまり、近代化しようとしたタイミングで価値観を無理やり変えてしまったことは多かったんじゃないかと。
吉田 明治以前の方が、今にフィットする考えや感覚があるってこと?
永井 それはある気がします。少なくとも江戸の文化のほうがゆるくて多様性はあった。いわゆる維新の志士よりも、例えば渋沢栄一さんのように幕臣から明治政府に入っていった人たちの感覚は今にも通じるなっていう気はしている。
明治の時代に「Nature」を「自然」と訳したわけだけど、自然にはもともとは「じねん」という意味があって。
吉田 自然薯の「じねん」ね。
永井 そう。でも自然(じねん)って直訳すると「あるがまま」。Natureをしぜんにあてたことでズレてしまった気がしていて。もちろん、海や山のようにあるがままにあれ、という感覚で行くと一理ある。でも、自然(じねん)には人間も含まれる。海、山、人は同列で、間違っても保護する対象ではない。花鳥の絵は、単に花や鳥がキレイだから書いているのではなくて、むしろ宗教観なんですよね。鳥があるがままにある様を見て、私たちもあるがままにあれ、のような。
吉田 それは確かに明治期にそこまで考えずに訳を付けた感はありますね。
永井 あるがままにとは、ある程度、自分の手に負えないことに関しては諦めるということ。それは重要な価値観で。要するに、手に負えないことのほうが多いわけだから。人の生き死にはもはや我々の手に届かないこと。それをどうにかできるという思いそのものが傲慢であり、それを他力本願という考えで、できなかったことに対する後悔を「しょうがない」と思い、南無阿弥陀仏=「阿弥陀仏におまかせします」と唱え、これで終わりと手放す。それはキリスト教のミサでもよくやること。仏教もキリスト教も、言っていることは似ている。いかに上手に、ラクに、心やすらかに生きるかみたいなことをやってきていることだから、ウェルビーイングに共通しているところがあるのかなと。
吉田 この連載でもよく話に上がるテーマが「しょうがない」。考えてみると、しょうがないはウェルビーイングを生むためのポイントなのかもしれない。しょうがない=手放すってこと。そうすることで気持ち的にウェルビーイングがやってくる気がする。国際競争力とか、そういうところから降りてもいいよねっていう感じするんだけどね。

「しょうがない」って考えは
ウェルビーイングを生むための
ポイントなのかもしれない
永井 そう。私たちは「その競争に勝っても楽しくなかった」と言うことをもう知ってしまっている。そこにしがみつくことは幸せにはつながらない。
吉田 江戸までのゆるゆるの中に、今のウェルビーイングに通じる価値観がありそうな気がするな。
永井 江戸だけじゃなく、奈良のころに作られた「出身法」では、すでに男女雇用機会均等法みたいなものがあった。「男女同じ基準で採用しよう。結婚していても、子どもいても関係ない。能力だけ確かめておいて」と書かれてある。
吉田 男女同権をもう説いているんだ。
永井 だから、心にかかっている不幸な思い込みを解くために、古典に立ち返ることの意味はある気がするんですよね。
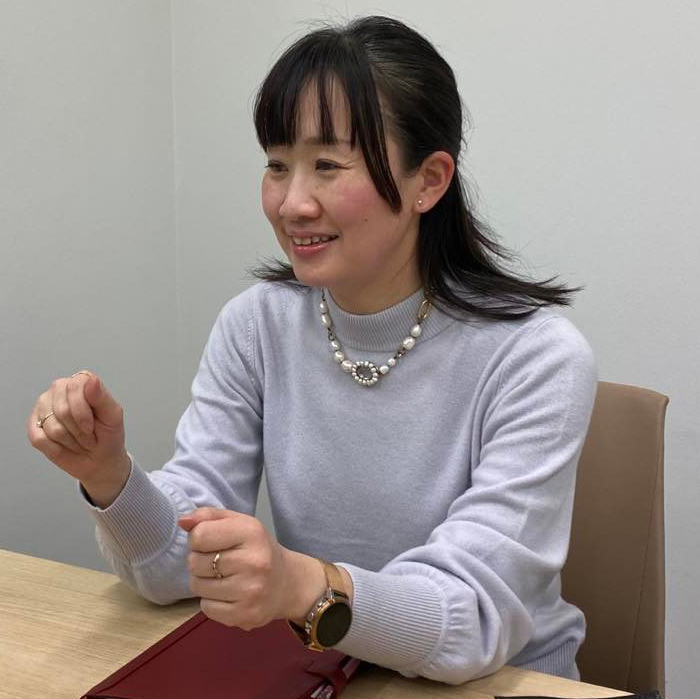
心にかかっている
不幸な思い込みを解くために、
古典に立ち返ることの意味がある気がする
吉田 昔話然り、今まで残ってきているのには理由があるわけですからね。
1975年12月12日東京生まれ。ニッポン放送アナウンサー。第49回ギャラクシー賞DJパーソナリティ賞受賞。「マンガ大賞」発起人。現在、『ミューコミVR』と週10本前後のPodcastを担当。最新刊は石川善樹氏との共著『むかしむかし あるところにウェルビーイングがありました』(KADOKAWA)。ほか著書多数。
ながい・さやこ
1977年神奈川県生まれ。新聞記者を経て、フリーライターに。2010年『絡繰り心中』で小学館文庫小説賞を受賞しデビュー。2020年刊行『商う狼 江戸商人杉本茂十郎』(新潮社)で第40回新田次郎文学賞、第10回本屋が選ぶ時代小説大賞受賞。『大奥づとめ』(新潮社)『横濱王』(小学館)など。新刊『女人入眼』(中央公論新社)発売中。
※この記事はコマーシャル・フォト2022年4月号から転載しています。











